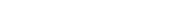
シリーズ連載中は、お二方とも読者の方の熱意がすごかったでしょう。

そうですね。熱烈すぎて、ラスと闇主が出なかったりすると、「私が待っているのは、闇主とラスが仲良くラブラブするところなのに! 全然、その気配もないじゃないですか!」というお手紙をどっさりいただきました。

前田さんは、『破妖の剣』と並行して書いているシリーズもあったから、「こっちを書いて」というリクエストも多かったのでは?

自分としては、連載を並行して書くことは、充電池がいくつもあるイメージなんです。一冊書くと、その作品を書くエネルギーを溜める充電池が減る。別のシリーズの、充電完了しているものを書いているうちに、こっちがまた、じわっ、じわっと充電が戻ってくる、というイメージでした。あとがきで次の執筆予定を書くこともありましたし、読者さんから「『破妖』を書いて」という声もありましたけど、「そんなに立て続けに書いてたら、充電なくなっちゃうじゃん」っていうのもあって(笑)。空っぽになったら、文字が出てこない。

『ミラージュ』は、雑誌連載と並行して書いてたときはありました。雑誌連載で本編の続きを書くわけにいかないので、番外編や時代設定を変えたシリーズを書いていました。
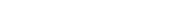
メディアミックスでアニメや舞台にもなっています。

アニメでエンディングテーマを歌ってくださった荒木真樹彦さんの大ファンだったので、ひたすらにエンディングだけを聴いていたいと思っていました。

アフレコにも行ったんですか?

ええ。あまりにもラスの怪我がひどいので、「えーっ!?」と思って、後で自分で読み返してみたら……。

間違ってなかった(笑)。

文章で書いてあるイメージでは、そこまでひどくないと思ってたけど、画像で見て声優さんの声で聴くと衝撃でした。「やだー、八重歯が体を突き抜けてるじゃん」って。

アニメでみてはじめてわかったなんて、すごいですね。

『前田珠子はサド』って言われる理由がわかりましたよ(笑)。いつも、文章で浮かべて書いてるから、そこまでめちゃくちゃいじめまくっているという自覚はなかったんです。ある程度傷ついてボロボロになったけど、その後の大逆転! という展開がファンタジーの基本だ、と思っていたので、物語性を高めるためにとことん劣勢にさせていたら、傷だらけになっちゃってた(笑)。

たまに身体に穴とか開いてませんでした?

穴も開けたし、えぐったし、手足が沸騰しそうになったりもしてます。

「よく思いつくな。こんな激しいアクション」と私は読んで思っていました。でもそういうシーンに、「厨二心」が刺激されてときめくんですよね。コバルトに初めて厨二心を持ち込んだのも前田さんですよ。

それは否定できないかも(笑)。でも、桑原さんも高耶をけっこういじめたでしょう。

まあ、やりましたけど、前田さんにはかないません(笑)。私は「ミラージュ」の舞台を観て、自分が書いてきた世界が三次元に存在することが可能なんだ」と実感できました。私の頭の中だけでやってる出来事が、実際の人間が演じているのを見て、うーん、何て言うか……「正解だった」でもないし「間違ってなかった」でもないし……そうだ、「三次元からお墨付きをもらった」という感触です。舞台は昭和編ですから、加瀬や尚紀を生身の人間の俳優さんたちが演じることによって、この世に存在しうる人間像なのだと確認できました。これは自分にとって、大きな意味がありました。直江役を演じた荒牧慶彦さんは、『ミラージュ』がスタートしたのと同い年生まれで、次の時代に物語をつなげてくださる次世代の方々が演じてくれたのも嬉しかったし、不思議な気持になりました。
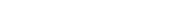
最後に、第一巻から最終巻までで、一番苦労なさった点を教えていただけますか?

始めたときの自分自身の価値観とか考え方は、だんだん、ストーリーが進むにつれて、歳を取っていくだけ、変わっていつつあって。そしたら、この世界観と、自分の意識が乖離しないように、どう折り合いをつけていくか、みたいな。若いときのままの世界を描いていったら、もう、心が、注げなくなっちゃうので、どうこの世界自体にも変化してもらって、今の自分が、心を入れて書けるようにするか、みたいなところが、ちょっと苦労しました。シリーズ全体の流れで言うと、鬱金の途中、パパが亡くなる前後ぐらいですね。

今おっしゃられたこと、とてもわかります。『破妖の剣』『炎の蜃気楼』ともに第一巻が出てから三十年近くたちます。始めたとき、本当にふたりとも若かったじゃないですか。その年月の分だけ、自分たちも、だいぶ、経験もしてるし、考え方も変わってるし、だけど書く世界は、これでないといけない。確かに、すごい、折り合いをつけるのが難しいなと思って。私も、ここに着地するために昭和編を書いてるんですけど、なんだかほんとに、そのときの自分の若さと未熟さを思い知らされますね。

そうそうそう(笑)。

そこに着地しなきゃいけないんだけど、そのままでは書けないじゃないですか。その、二十代のときの物の見方や感覚には、なかなか心が入っていけないんですよね、まさに。

はい。

そこを、自分の中でどう咀嚼して、今の感覚で、それをちゃんと着地できるかというところは、たしかに、心を砕きました。

だって二十年以上前の、自分の書きだしたやつをよ? おんなじ気持ちでいられたら、人間として、ねえ?(笑)。

ヤバイですよねえ(笑)。そうですよ。(何十年たっても)「そのままでした」みたいなのはねえ、ちょっと、人として。

うん。成長もなんもしとらん、っていうことに。

そこまで純粋ではいられないですよね(笑)。
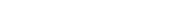
それは読者の方も同じかもしれません。シリーズが完結したことで「最初から全部読み返したい」という方もいらっしゃると思います。きっと自分の年齢に応じた読後感が得られるに違いありません。

終わったからこそ、読者さんにも安心して読み返していただけるでしょうね。

私たちも完結したから、安心しています。

ええ、もう充分に書きました。

長い間、ご愛読ありがとうございました。
【終わり】
(司会・構成=烏兎沼佳代)